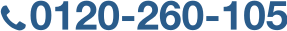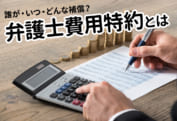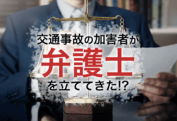弁護士費用特約は家族でも使えるのか|利用の範囲とは?

自動車保険の弁護士費用特約(弁護士特約)は、万が一交通事故に遭ってしまい、弁護士に依頼をしなければならなくなった場合に、弁護士費用を保険会社に支払ってもらうことができる便利な保障です。
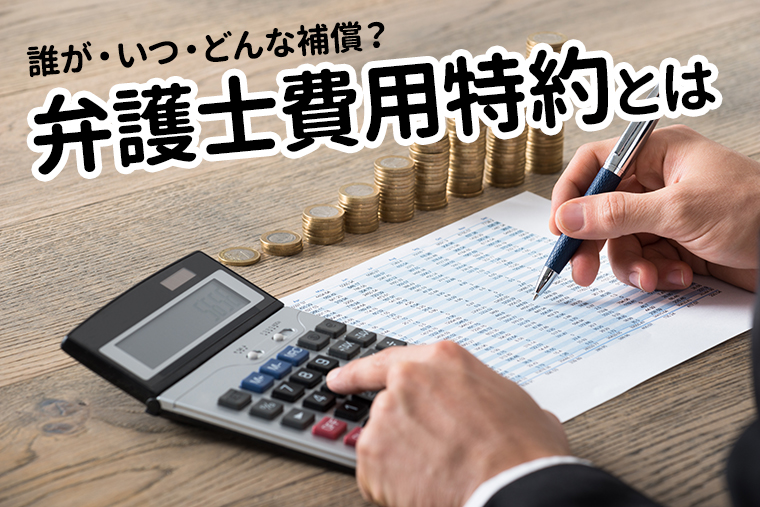
[参考記事]
弁護士費用特約とは?|誰が、いつ、どんなことを補償されるか
この弁護士費用特約は、家族のうち誰か一人が加入していれば、他の家族が交通事故に遭った場合にも利用できる可能性があることをご存知でしょうか。
もし交通事故に遭ってしまったら、ご自身が自動車保険の弁護士費用特約に加入していなかったとしても、家族の誰かが付けている弁護士費用特約を利用できるかどうかを忘れずに調べてみましょう。
(家族が各々違う車を所持して、違う保険会社に加入していた場合でも、被保険者の家族ならば弁護士費用特約が利用できることがあります。)
この記事では、自動車保険の弁護士費用特約を被保険者の家族が利用できるケースについて解説します。
1.弁護士費用特約の保障範囲は契約内容次第
弁護士費用特約がどの範囲で利用できるかについては、保険契約の定めによって決まります。
したがって、被保険者の家族が交通事故に遭った場合に弁護士費用特約を利用できるかどうかについても、保険契約の内容次第ということになります。
具体的にご自身のケースでご家族が弁護士費用特約を利用できるかどうかについては、必ずご自身が加入している自動車保険の弁護士費用特約に関する契約内容を確認するようにしてください。
2.保険契約の確認内容
まず、自動車保険被保険者の家族が交通事故に遭った場合に、弁護士費用特約を利用できるかどうかについて確認する際、保険契約においてどのような内容をチェックすれば良いのかについて解説します。
(1) どの程度近しい家族・親族まで利用可能か
保険契約上、弁護士費用特約を利用できる家族・親族の範囲を決定するためのポイントの一つとなるのが、「被保険者との関係性(親族関係)」です。
一例としては、被保険者と以下の関係にある者については、被保険者の弁護士費用特約を利用できる場合が多いといえます。
- 配偶者
- 子
- その他の親族
なお「親族」とは民法上、①六親等内の血族、②配偶者、③三親等内の姻族を指すものとされています(民法725条)。
自動車保険における弁護士費用特約の内容上も、民法上の親族の範囲と同じ範囲で、弁護士費用特約の利用を認めることが多いようです。
(2) 被保険者との同居の要否
被保険者の親族に該当すれば誰でも被保険者の弁護士費用特約を利用できるわけではなく、一部の親族については、被保険者と同居していることが利用の条件になっていることもあります。
一般的には、配偶者と未婚の子については、被保険者と同居しているか否かを問わずに弁護士費用特約を利用できる場合が多いようです。
これに対して、配偶者と未婚の子以外の親族については、被保険者と別居していない場合に限り、被保険者の弁護士費用特約を利用できるパターンが多くなっています。
(3) 運転していた車の名義について
家族・親族が交通事故に巻き込まれるケースでは、被保険者の車ではなく、交通事故に遭った家族自身が所有する別の車を運転していたという場合もあるでしょう。
また、被保険者本人が、家族が所有している車を運転している際に交通事故に遭うケースもあるかもしれません。
他人名義の車を運転していた際に弁護士費用特約を利用できるかどうかも、保険契約の内容次第で決まります。
そのため、保険契約の規定上の弁護士費用特約の保障対象に、被保険者名義の車で交通事故に遭った場合だけが含まれるのか、それとも他人名義の車で交通事故に遭った場合でも保障対象なのかについて確認しましょう。
なお、保険契約の内容によっては、被保険者本人が交通事故に遭った場合と、家族が交通事故に遭った場合とで、保障の範囲を変えているケースもあります。
たとえば以下のように、被保険者本人と家族・親族の場合で結論が変わることもあり得ます。
- 被保険者本人が交通事故に遭った場合
→被保険者名義の車だけでなく他の車を運転していた場合であっても弁護士費用特約を適用可能 - 家族や親族が交通事故に遭った場合
→被保険者名義の車を運転していた場合に限り弁護士費用特約を適用可能
この点については、事前によく保険契約の規定文言を確認しておくことが重要です。
3.弁護士費用特約の利用範囲についても一度弁護士に相談を
弁護士費用特約を利用できるかどうかを把握するには、保険契約の内容を読み解く必要があります。
しかし、保険契約の内容は非常に込み入っており、また場合分けが細かくされていることも多いため、実際に弁護士費用特約を利用できるかどうか判断が難しいという場合もあるでしょう。
その際には、一度弁護士に相談をして、弁護士費用特約が利用できるかどうかを確認することをおすすめいたします。
弁護士費用特約の利用可否を確認するのと同じ機会に、交通事故の概要などを説明してアドバイスを受けておけば、その後の依頼にスムーズに繋げることもできます。
まずはお気軽に、泉総合法律事務所の弁護士までご相談ください。